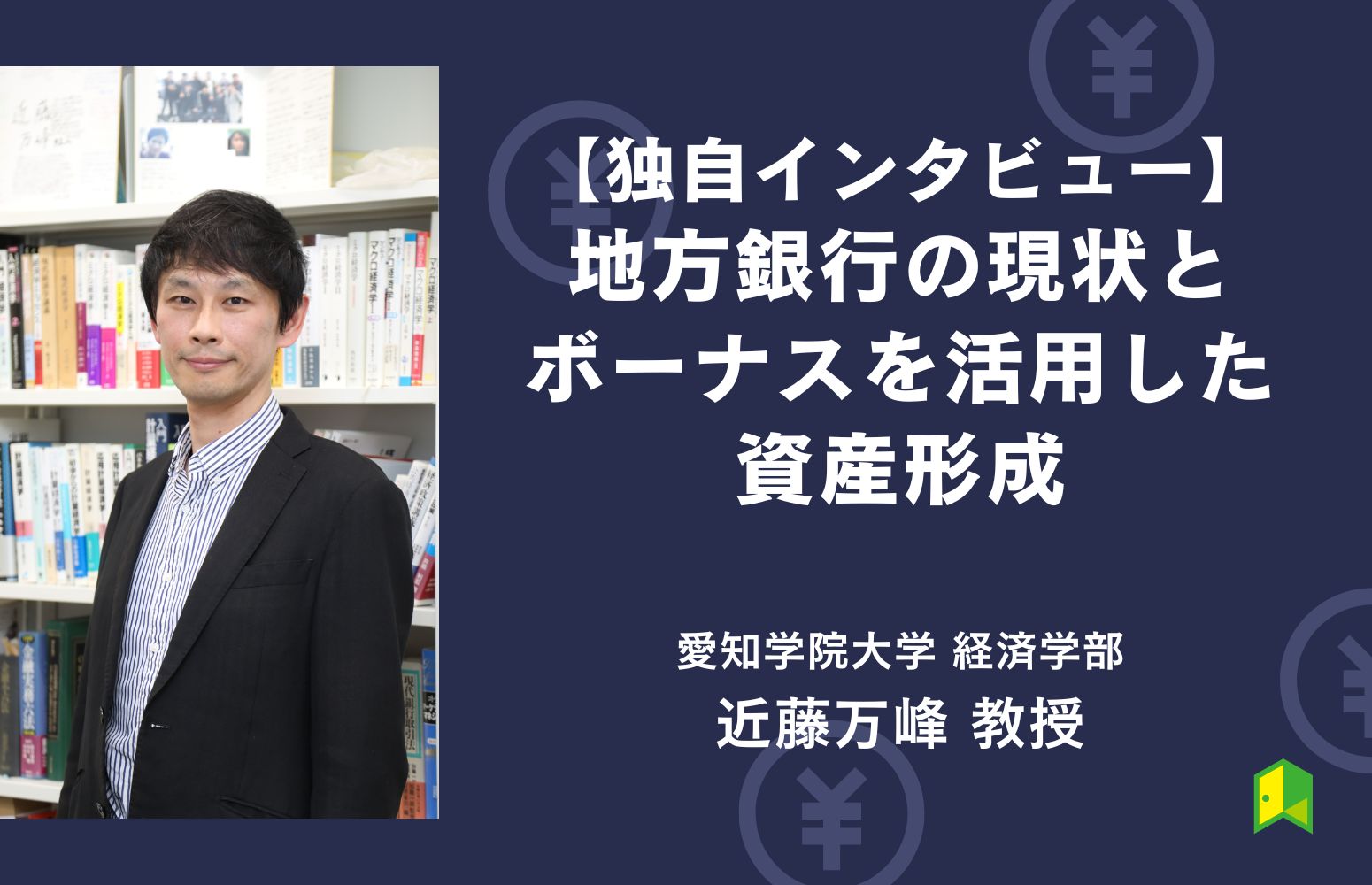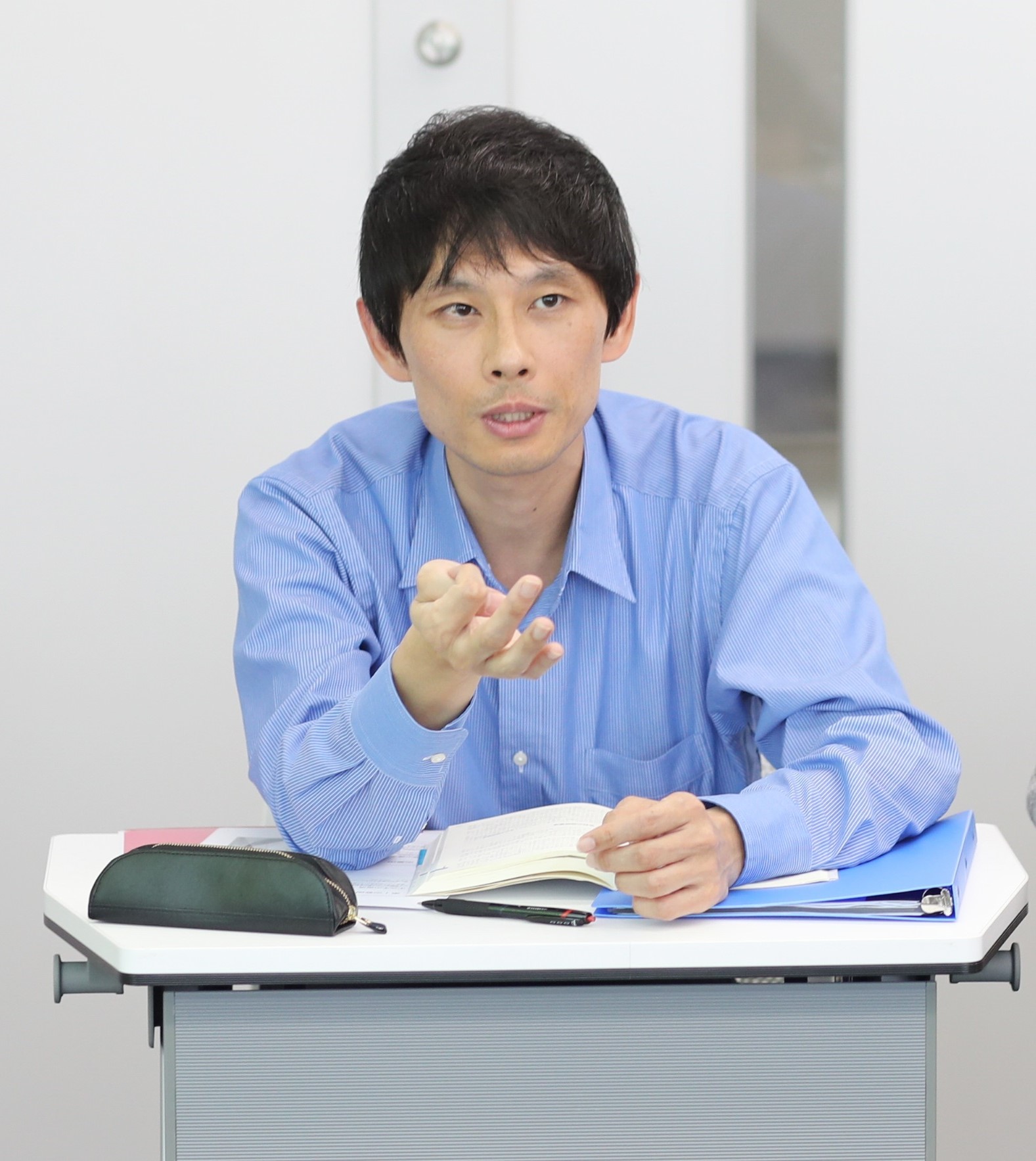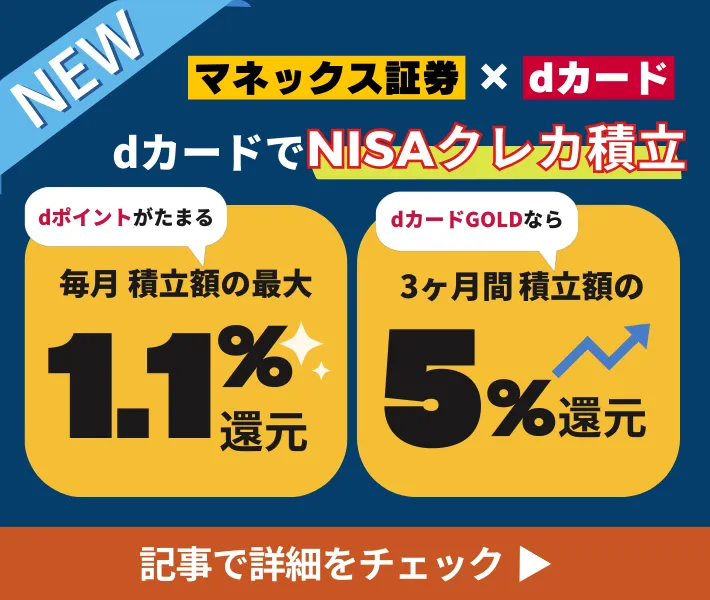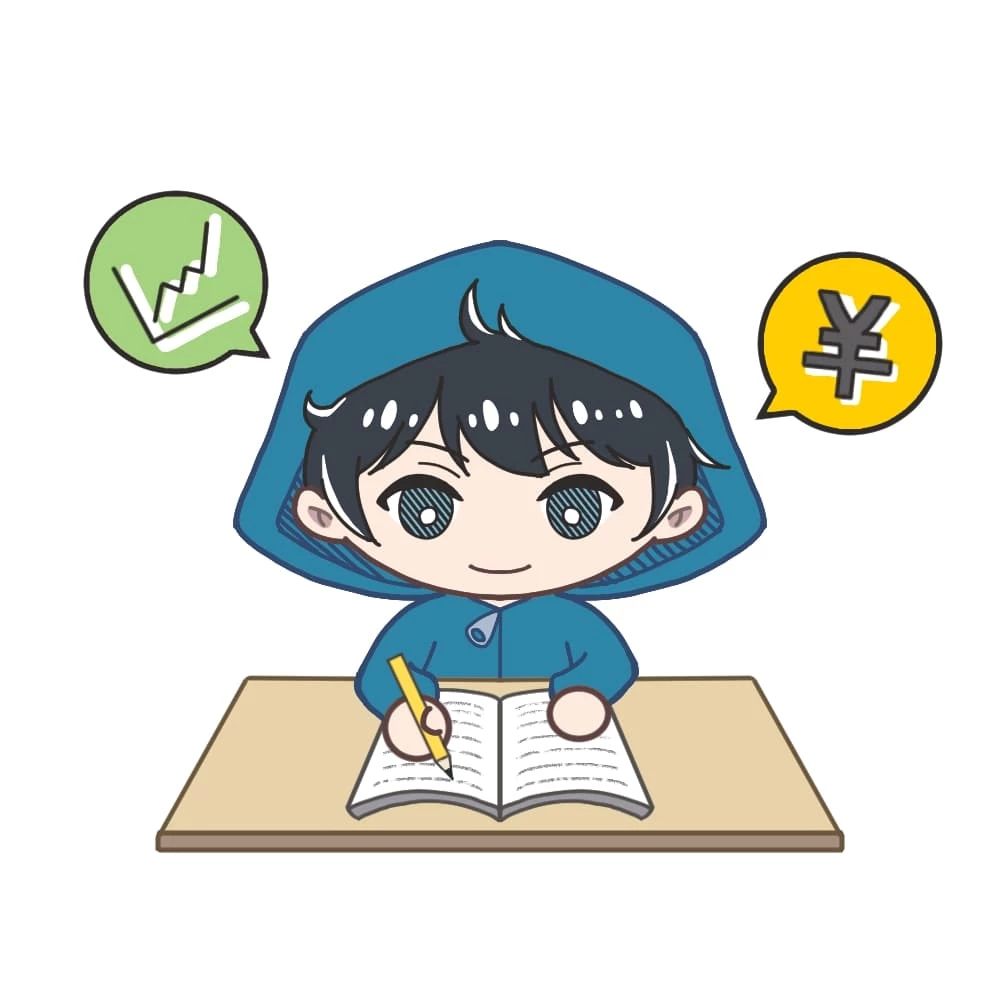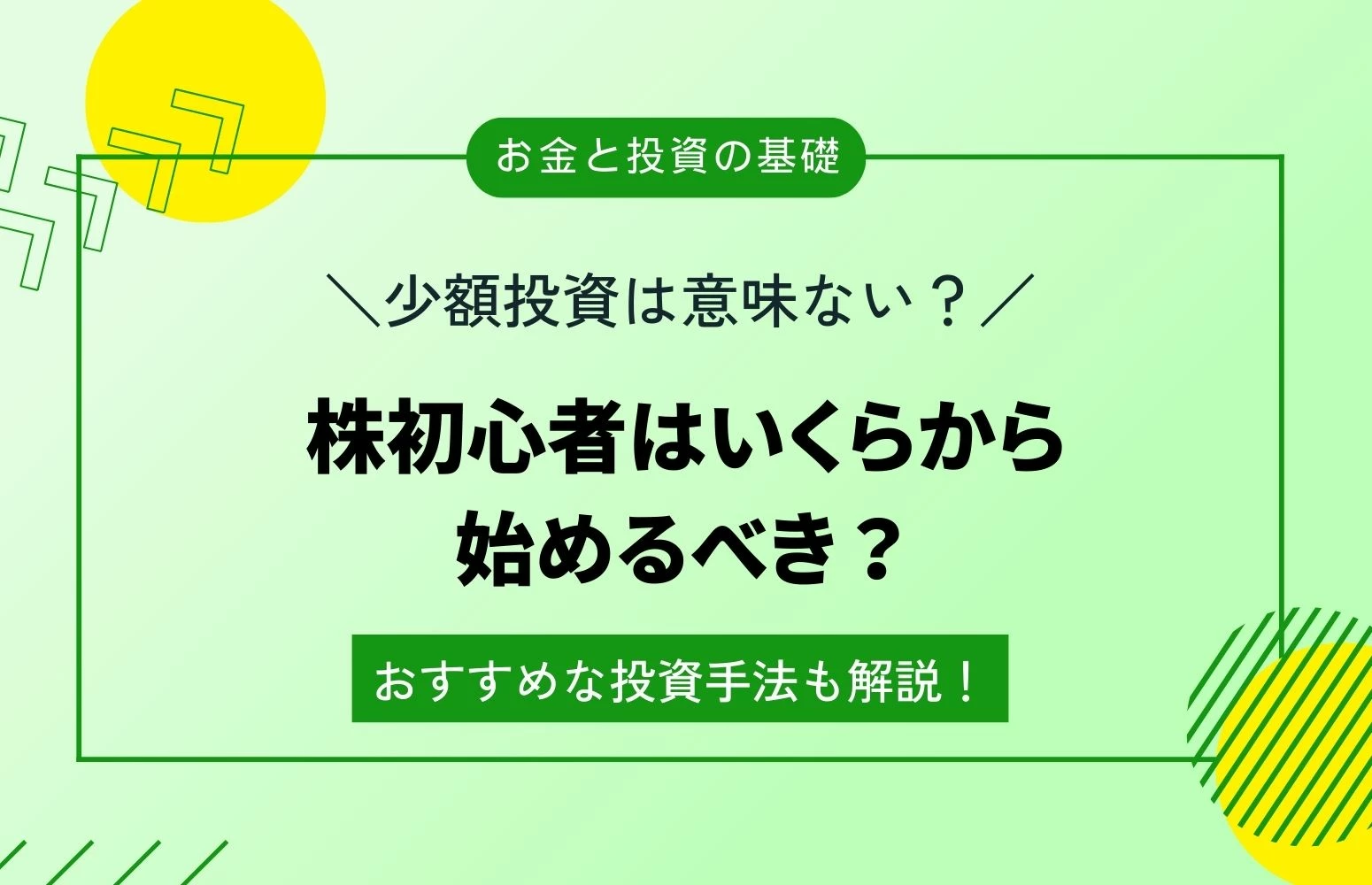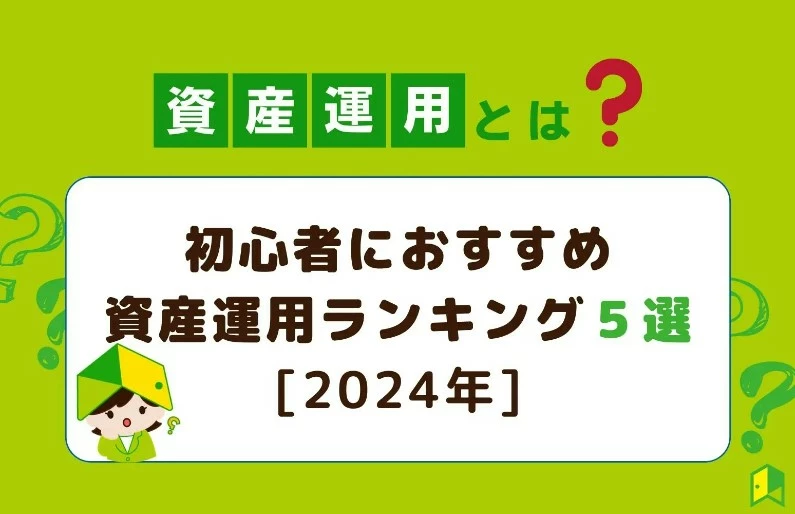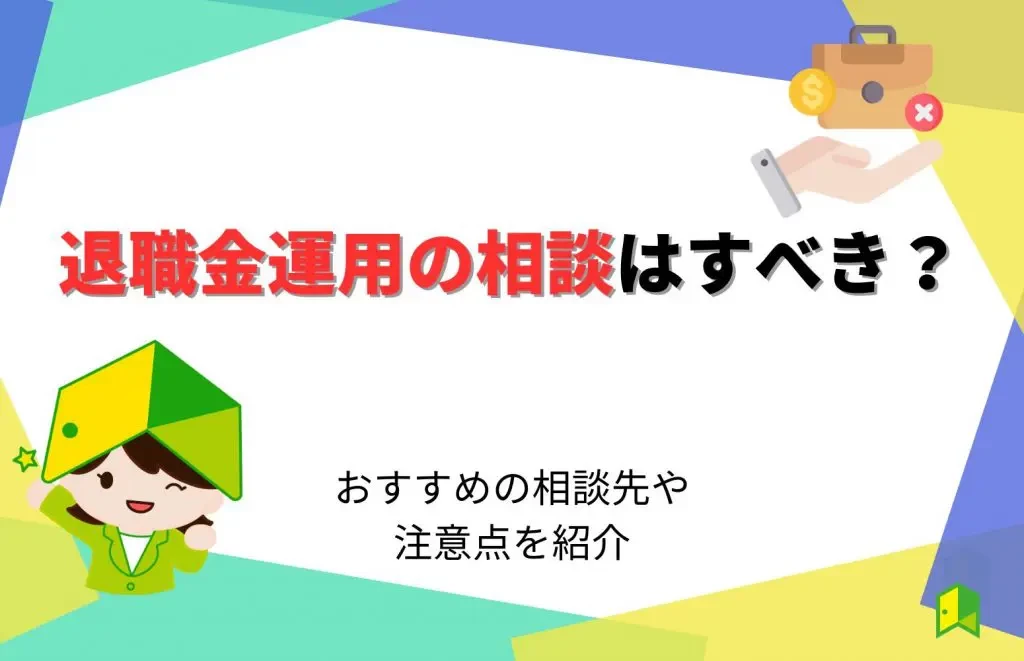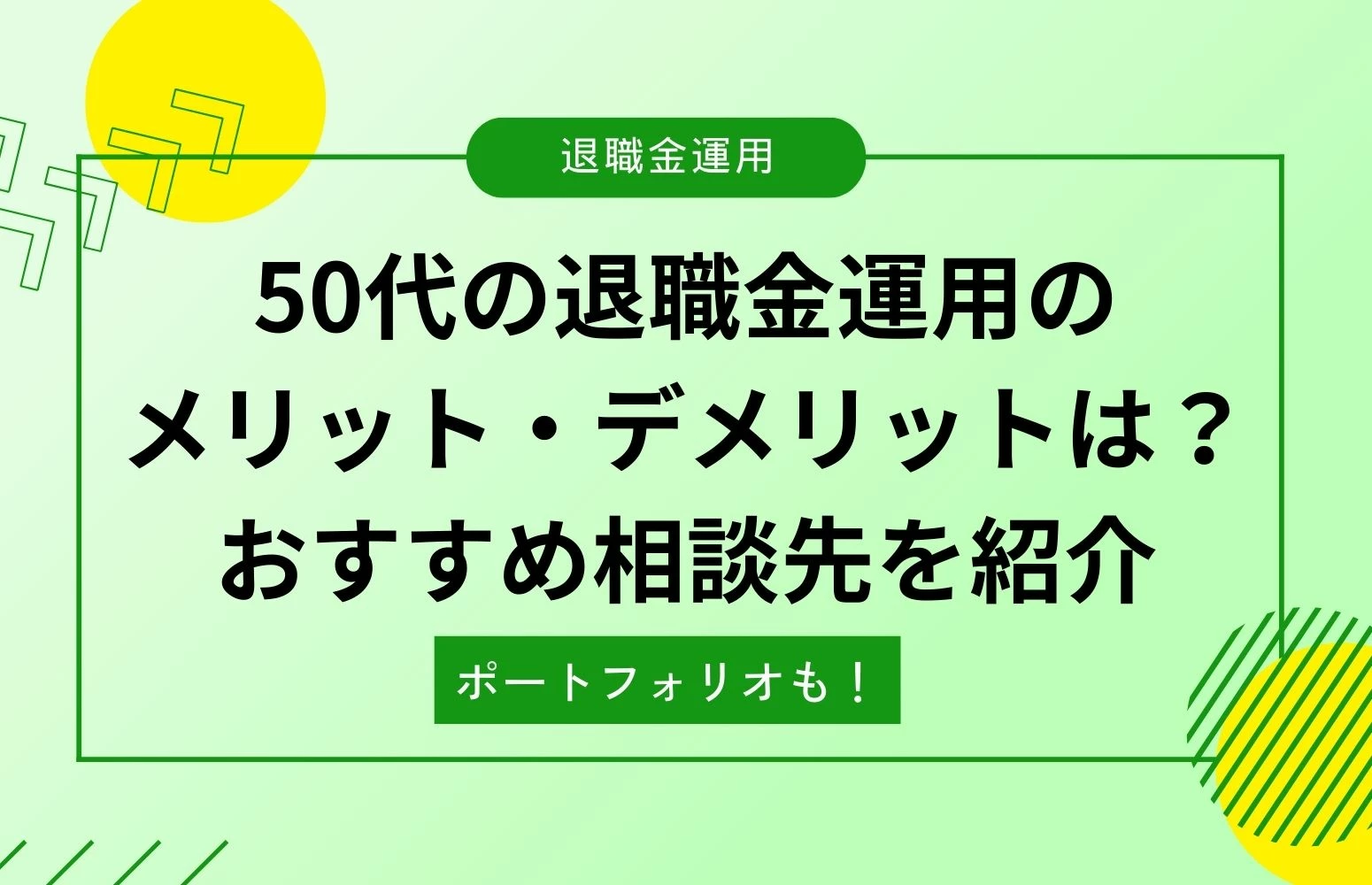2024年から新しいNISAがスタートしたことに伴い、資産運用を始めた方や始めようと思っている方も多いと思います。
とはいえ投資経験のなかった方には、どのような点を意識して取り組めば良いのか悩んでいる方も多いはず。
そこで今回は、愛知学院大学にて金融論、中でも金融システムの研究をされている近藤 万峰教授にインタビューを実施。
地域銀行の課題や将来性、後半ではボーナスを活用した資産運用について考えをお聞きしました。
地方銀行の課題と将来性は?
—近藤先生が金融システムの中でも特に地域金融に興味を持たれたきっかけを教えていただけますか?
近藤教授:実は日本の企業は、99%が中小企業で占められています。
一般的に、中小企業は大企業と異なり情報の非対称性が大きいので、株式や社債の発行による資金調達が困難です。
そのため、資金供給の担い手という側面において、地域銀行(地方銀行と第二地方銀行)(以下:地方銀行)をはじめとする地域金融機関の果たす役割は非常に大きいです。
また、地方創生が叫ばれる中、創業支援や経営支援においても地域金融機関に期待される役割は拡大しています。
そういった中で、地域や地域金融機関に注目することの意義は高いと考えています。
—メガバンクをはじめとする都市銀行と地方銀行ではどのような役割の違いがありますか?
近藤教授:地域金融機関が果たす役割は、地域の中小企業と親密なリレーションシップを構築して、資金供給や経営支援といったサービスを提供することです。
一方で、メガバンクはいわゆるトランザクション・バンキングを中心とし、グローバルに多角的な事業を展開しています。
そのため、両者の性質には相違があり、果たすべき役割も自ずと異なってくるでしょう。
—地方銀行が現状抱えている課題とそれに対する解決策についてどのようにお考えでしょうか?
近藤教授:地方銀行の特性上、地域と運命共同体になってしまう側面があることを否定できません。
これからの時代において、地方の人口減少は避けられませんし、それに伴う廃業なども増えてくるでしょう。
そういった中で、貸出による利息収入を増やす戦略だけではどうしても限界があると考えています。
創業支援や経営支援にも注力することで、その地域に新たな産業を生み出したり、有力な製品・サービスや地元産品を生み出したりすることが求められていくのではないでしょうか。
—都市部と比較して、スタートアップが少ないことも地方の課題だと考えています。これに対して地方銀行はどのような対策を行うべきでしょうか?
近藤教授:比較的最近になって、人材紹介業が解禁されました。
大企業の役員クラスの方が地方への移住を希望されるケースは意外にも少なくないのではないでしょうか。
そういった高いビジネスのノウハウを持った方々を地方へ移動させる際に、地域金融機関が力になれそうだと考えています。
これまで培ってきた企業間のビジネスマッチングのノウハウに加え、都市部から地方への人の流れを作っていく強みが生まれたらますます可能性は広がるでしょう。
投資対象として見たときの地方銀行株の評価は?
—ここからは、少し視点を変えて地方銀行を投資対象として考えてみます。
足下のPBRを見ると、地方銀行株は1倍を割っている印象があります。市場から評価されない理由はなぜでしょうか?
近藤教授:大きな理由は、地方銀行の改革や取り組みに改善の余地があり、マーケットから必ずしも高く評価されていないことにあると考えます。
また、メガバンクや大手保険会社と比較すると、投資家から注目されにくい業種であることも理由の一つでしょう。
—割安感のある地方銀行株ですが、今後の展望はどのようにお考えでしょうか?
近藤教授:3月にマイナス金利政策等が解除され、保有債券の含み損が発生する副作用はあるものの、今後ゆっくりと進んでいくであろう金融引き締めは、地方銀行をはじめとする金融機関にとって追い風だと思っています。
ただ、地方銀行は公共インフラの側面が強いので、短期的なキャピタルゲインはあまり期待しないほうが良いでしょう。
一般的な投資スタンスとして、短期的な値上がりを期待するのであれば向いていない業種でしょう。
一方で、地域によって今後の展望が異なる部分があるのも事実です。
ボーナスは投資に回すべき?
—続いて、資産形成に関して伺います。
ボーナスのような臨時収入のおすすめな使い道はありますか?
近藤教授:普段頑張っているご褒美として、自分に使うことも当然大切だと思います。
残りの部分を何らかの形で貯蓄に回すのが一般的ではないでしょうか。
気を付けてほしいのはボーナスに限った話ではないですが、入ってきた臨時収入を全部使い切ってしまわないことです。
これからの時代、年金財政など不透明な部分がありますので、ある程度資産形成に回していく必要があると思います。
—資産形成をする上で気を付けるべきポイントはありますか?
近藤教授:投資は余剰資金の範囲内で行うことですね。
また、各自の性格によって取るべきリスク量が変わってくる点に注意が必要です。
たとえば、リスク回避傾向が強い性格の人であれば、多くの割合を投資に向けてしまうのは危険でしょう。
ただ、物価の上昇に伴うインフレリスクのことを考えると、ある程度の資金を投資に回すのが望ましいと個人的には思っています。
—年齢によって取れるリスクの量は変わってきますか?
近藤教授:年齢という観点から考えると、少しずつ保守的なポートフォリオに組み替えていくべきだと考えます。
逆に、長期投資ができる若い年代であれば、インデックス投資などで中長期的なリターンを狙っていくのも良いでしょう。
高齢の方は、債券や預貯金の割合を増やしていくことが無難だと思います。
投資に興味を持つ若者へのメッセージ
—最近では、投資に興味を持っている若い方も増えています。若い世代に向けてのメッセージやアドバイスなどあれば伺いたいです。
近藤教授:繰り返しにはなりますが、前提として投資は余剰資金の範囲内で行いましょう。
また、各自のリスク選好度に応じてリスク資産と安全資産の保有比率を決めるべきです。
もっとも、投資は長期的な視点が必要となります。
下落相場のタイミングですぐ投資をやめてしまったり、短期目線で売買を繰り返したりするより、長期的な目線を持ち、インデックスファンドなどの積立投資によって資産形成していくことが多くの方にとって望ましいと考えています。